日本の病院受診、実際のところは?
私はこれまで大阪に住みながら、大きな病院から小さな病院までよく利用してきました。しかし、日本で初めて病院に行ったときは、健康保険証(2024年12月からはマイナンバーカードに統合)を持参しなければならないということ以外にはほとんど何も知らず、日本の医療システムについても全く理解していなかったため、困ったことが何度かありました。
日本の医療システムは高い品質で知られており、便利な点も多いですが、不便だと感じる部分が残っているのも事実です。特に病院にあまり行かない日本人や外国人にとっては、慣れていないため戸惑うこともあるでしょう。
私は外国人ではありますが、日本語には不自由しないため、診察や治療で困ったことはありませんでした。ただし、韓国の病院とは違う点も多く感じました。
この文章では、私が日本で病院を利用しながら知った主な特徴を整理しました。日本に住んでいる方や長期滞在を予定している方にとって、少しでも参考になれば幸いです。また、ここに書ききれなかった内容については、別の投稿でもまとめてありますので、ぜひ併せてご覧ください。
– こちらの記事もおすすめ –
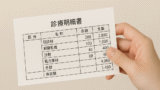
日本で病院を使うときに知っておきたいこと

1. 英語診療は限定的
日本では、大都市の一部の大病院を除き、英語で診療を受けられる機会はそれほど多くありません。特に地方や小規模な病院では、外国語に対応できる医療スタッフを見つけるのは難しいのが現状です。日本語が十分にできない場合は、自分の症状を正確に伝えにくく、医師の説明を理解するのも大変かもしれません。
そのため、できれば日本語ができる知人と一緒に行くか、通訳サポートのある病院を利用するのがおすすめです。近年では、外国人患者に対応するために英語・中国語・韓国語など多言語サポートを行う病院も増えてきていますので、事前に調べて自分の住んでいる地域でそうした病院を把握しておくと、より安心できるでしょう。
2. 病院間の情報共有が円滑ではない
日本の医療システムも徐々にデジタル化や近代化が進んでいますが、病院同士の情報共有は依然として十分に円滑ではないことが多いです。病院を変える場合、以前の病院で受けた検査結果や診療記録が自動的に引き継がれないため、同じ検査を再度受けなければならなかったり、患者本人が書類を準備して持参しなければならないことがあります。
特に長期的な治療や精密検査が必要な場合には、この点が不便に感じられることも少なくありません。そのため、必要な資料は事前に依頼してコピーをもらい、次の病院に提出できるように準備しておくと安心です。
3. セカンドオピニオンは可能だが手続きが必要
日本でも、診断や治療方針についてセカンドオピニオン(他の医師の意見)を受けることは可能です。ただし、多くの場合は紹介状の提出や追加費用が必要となります。また、予約制であることも多いため、正規の手続きを踏まなければ簡単に受けられるものではありません。
治療に不安を感じたり、他の医師の診断を参考にしたい場合は、まず担当医に正式に相談し、紹介状を依頼するのが一般的です。事前に手続きや費用を確認しておけば、余計な戸惑いを減らし、安心して治療方針を決定することができます。
4. 予約をしていても待ち時間が長いことがある
日本では予約をして病院に行っても、実際に診察を受けるまでに30分から1時間以上待つことは珍しくありません。特に有名な病院や大学病院では、患者数が多いため待ち時間がさらに長くなることもあります。
診察の時間が遅れるのはよくあることなので、病院に行く際は他の予定に余裕を持たせておくのがおすすめです。また、病院によっては受付後に待ち状況をモニターやアプリで確認できる場合もあるので、事前に確認しておくと便利です。
5. 病院の診療時間は短く、週末診療は限定的
日本の一般的な病院の診療時間は平日の午前9時から午後5時頃までで、昼休みに診療を行わないところも多くあります。夕方以降や週末、祝日は休診となる病院がほとんどで、救急でない限り診療を受けるのは難しいのが実情です。
そのため、病院に行く前には必ず診療時間を確認しておく必要があります。特に平日の日中に時間が取りにくい社会人や学生は、夕方や土曜午前に診療している病院を事前に調べておくと便利です。また、救急医療センターや夜間・休日診療クリニックの場所を把握しておけば、いざというときに安心できます。
– こちらの記事もおすすめ –


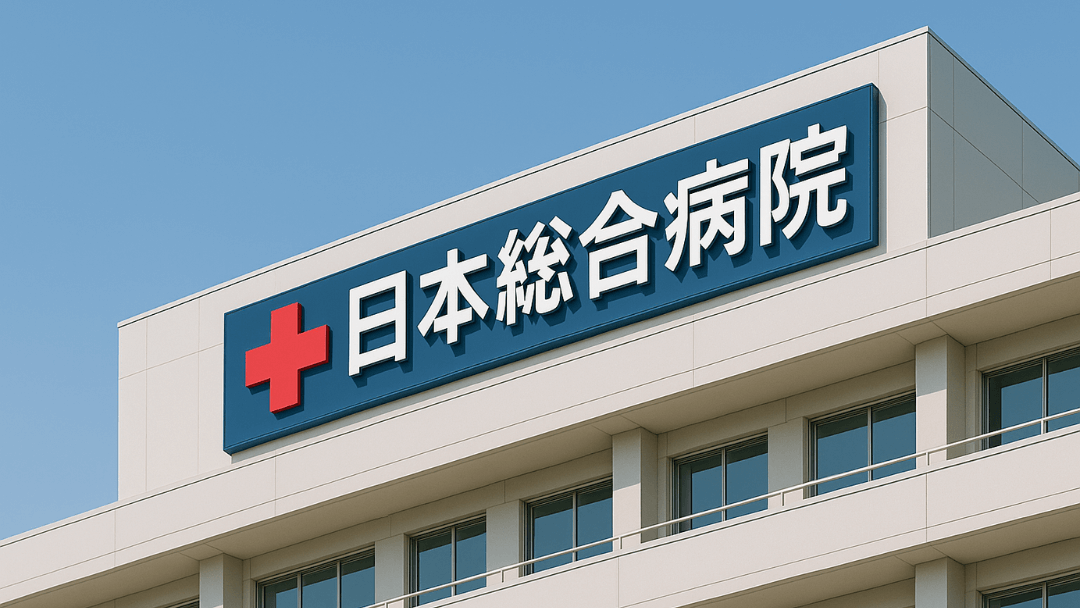
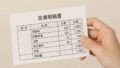
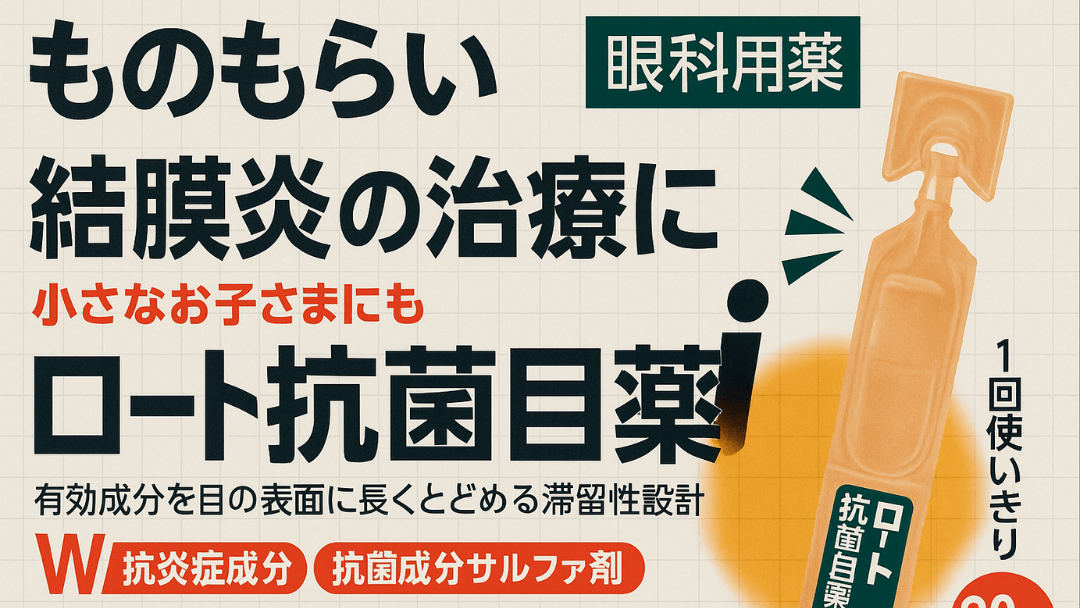
Comments